- 本記事にはネタバレが含まれます。
はじめに
『ブルーロック』の281話で新たな哲学、「天才」、「秀才」という概念が登場しました。
「天才」と「秀才」、果たしてそれぞれはどのように定義されるのでしょうか?
本記事では、まず「天才」と「秀才」という概念について、その定義と特性を整理していきたいと思います。
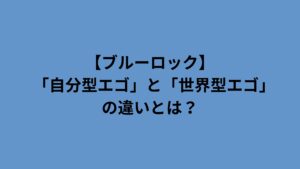
「天才」と「秀才」の定義
天才の定義は?
まず、「天才」とは、生まれ持った直感やセンスを武器に、瞬時に状況を判断し、他者にはない独自のプレーを展開する選手です。
フィールド上で独創的な技を見せることが多く、そのプレースタイルは、理論をあまり意識せず、自然体で自らの能力を発揮するため、時として予測不可能な動きをすることが特徴です。
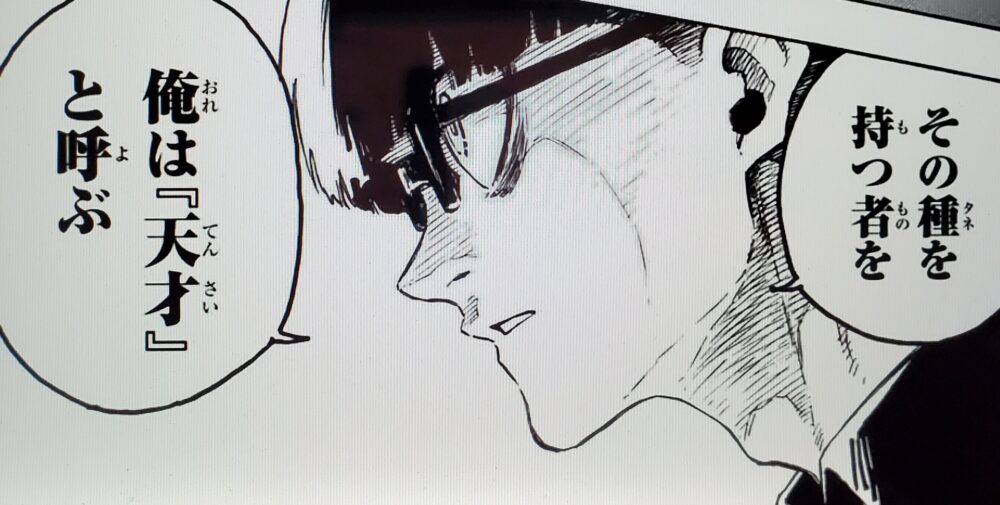
・凪 誠士郎
・ジュリアン ロキ
・士道 龍聖
・糸師 凛
・蜂楽 廻
・馬狼 照英
秀才の定義は?
一方、「秀才」とは、論理的思考、戦術の理解を基に、フィールドの未来を予測して最善のプレーを目指します。
秀才型の選手は、フィールド全体を俯瞰して状況を分析し、チーム全体を牽引する力を持っています。彼らは、明確な戦略に基づき、計算された動きで試合を組み立て、個々の技術と知識を合理的に活かすことで成果を上げるのです。
・潔 世一
・ミヒャエル カイザー
・烏 旅人
・御影 玲王
・シャルル シュヴァリエ
・マルク スナッフィー
・オリヴァ 愛空
このように、天才は直感と個の力、秀才は論理を重視する傾向にあります。
また天才=自分型エゴ、秀才=世界型エゴの持ち主であると判明しています。
絵心の理論
絵心の才能に対する持論として、「天才」は他とは違う特別な特徴をもって生まれてきます。 しかし、他とは違う特徴を持った人間は理解されなかったり、生きづらかったりします。
しかし、その人間が生む、時代や環境にマッチした革新的な表現が世界の標準を変えることがあり、その種を持つ人間が「天才」と呼ばれます。
しかし、その革新は現代社会の中では一人で成し遂げられるものではありません。
その天才の種を「見つけ」、「価値を理解し」、世界に「伝える」という別の才能が必要であり、その再現性を高めて、世界の標準にしていくことができる人間が「秀才」と呼ばれます。
つまり、ブルーロックの中では
規格外の身体能力やスーパープレーを放つ突然変異の「天才」が特異点の存在となり、
それを分析し戦術を生み出したり、対策するためにデータを駆使して「秀才」は新しい論理でプレーを新設計していきます。
「天才」と「秀才」は両輪である
秀才と言えば天才には劣る存在だという認識がありますが、「ブルーロック」の世界ではそうではありません。
潔世一もロキの圧倒的な才能に、秀才は天才に勝てない と絶望していましたが、「秀才」側であるカイザーが天才たちとやりあえてる様子を見て考えが変化していきます。
「秀才」が存在するおかげで「天才」はみつけてもらい、憧れあったり、いがみ合ったりすることで進化していく刺激しあう相対関係なんです。
超越視界(メタビジョン)が使えるのは秀才だけ?
『ブルーロック』において、超越視界(メタビジョン)は試合を左右する重要な能力になっています。
超越視界(メタビジョン)とは周辺視野によって全体を捉えながら、多くの情報を得ることで、ゲームの中で何が起きるかを理解しつつ、誰が何を狙って動いているのか、次に何が起こるのか、頭の奥で同時に高速処理を行うことで、フィールドの未来を予測できる能力です。
常に相手を分析して行動する必要があるため、「秀才」型のプレーヤーしか超越視界(メタビジョン)は使えないのだと思います。
実際に超越視界(メタビジョン)を使っているプレーヤーは烏旅人や、シャルル、潔や、カイザーなど秀才型です。
天才と秀才の異なる領域
天才型の選手は生まれ持った直感や感性でプレーするため、論理や計算に頼ることなく、瞬間的な判断で試合の流れを切り拓きます。
しかし、天才が無理に秀才型のプレー、すなわち計算された動きを模倣しようとすると、逆にその本来の強みを失い、パフォーマンスが低下する場合があります。
例として、天才型のネスは、秀才型のカイザーに合わせるために、自分の発想を殺しながら、カイザーを探しながらプレーをしていたことで、天才本来の独自の発想がなくなり、本来のパフォーマンスが出せていなかった可能性があります。
また、糸師凛も糸師冴が海外に行った後、糸師冴のようなプレーを再現しようとしていたせいで、天才型である糸師凛本来のパフォーマンスが出ていなかった可能性があります。実際に糸師凛との初対戦時では糸師凛が秀才型のような描き方がされていましたが、現在は、天才型のプレーヤーとして覚醒しています。
おそらく秀才型も天才型のようにプレーをしようとするとパフォーマンスが低下するでしょう。
このように、「天才が秀才のように、秀才が天才のようにプレーしようとするとパフォーマンスが落ちる」という事が考察できます。
ノエル・ノアは「天才」か「秀才」か?
ノエル・ノアは、作中で世界最高のストライカーと称される存在です。そのプレースタイルを見ると、「天才」と「秀才」のどちらの要素も持ち合わせているように見えます。
彼は天才のように圧倒的な才能と技術を持ち、個の力で状況を打開する能力に長けています。誰も真似できないプレーを生み出せるのは、まさに「天才」の特徴です。
しかし一方で、ノエル・ノアのサッカーは非常に合理的で、冷静な判断のもとにプレーしています。無駄を省き、チーム全体を考えた戦略的なプレーを好む点は、「秀才」的な要素といえます。
しかし、作中でノエル・ノアがメタビジョンを使っている描写はなく、潔の理論を興味深く聞いていたことからも、秀才的な思考を極めているというよりは、やはり天才寄りの選手ではないかとも考えられます。ノアは生まれ持った才能を最大限に活かしながら、独自の理論を築き上げているタイプであり、秀才とは異なるアプローチでサッカーを極めているのかもしれません。
また、過去に秀才型の絵心甚八と天才型のノエル・ノアが競い合っていたのではないか、と考えられます。もしそうであれば、ブルーロックの根幹にある「世界一のストライカーを生み出す」という理論は、秀才と天才のせめぎ合いの中で生まれたものなのかもしれません。ノエル・ノアは、天才と秀才の境界線上に立ちながらも、やはり「天才寄りのプレーヤー」としてサッカーの頂点に君臨しているといえるでしょう。
まとめ
ここまで、『ブルーロック』における「天才」と「秀才」の違いについて掘り下げてきました。
まず、「天才」とは、直感的なプレーや圧倒的な才能を持つ選手のことを指し、作中では凛や士道が代表例として挙げられます。一方で、「秀才」は、戦術や分析を駆使し、合理的にプレーする選手を指し、潔やカイザーが該当します。
次に、天才と秀才の違いがプレースタイルにどう影響するのかを考察しました。天才は自由な発想と個の力で試合を動かし、秀才は戦術理解と合理性で勝利を引き寄せます。しかし、お互いの特性を無理に取り入れようとすると、本来の強みが発揮できず、パフォーマンスが落ちることもあります。
これからの『ブルーロック』の展開では、天才と秀才がどのように協力しあったり、競い合ったりしてレベルアップしていくのか楽しみですね!

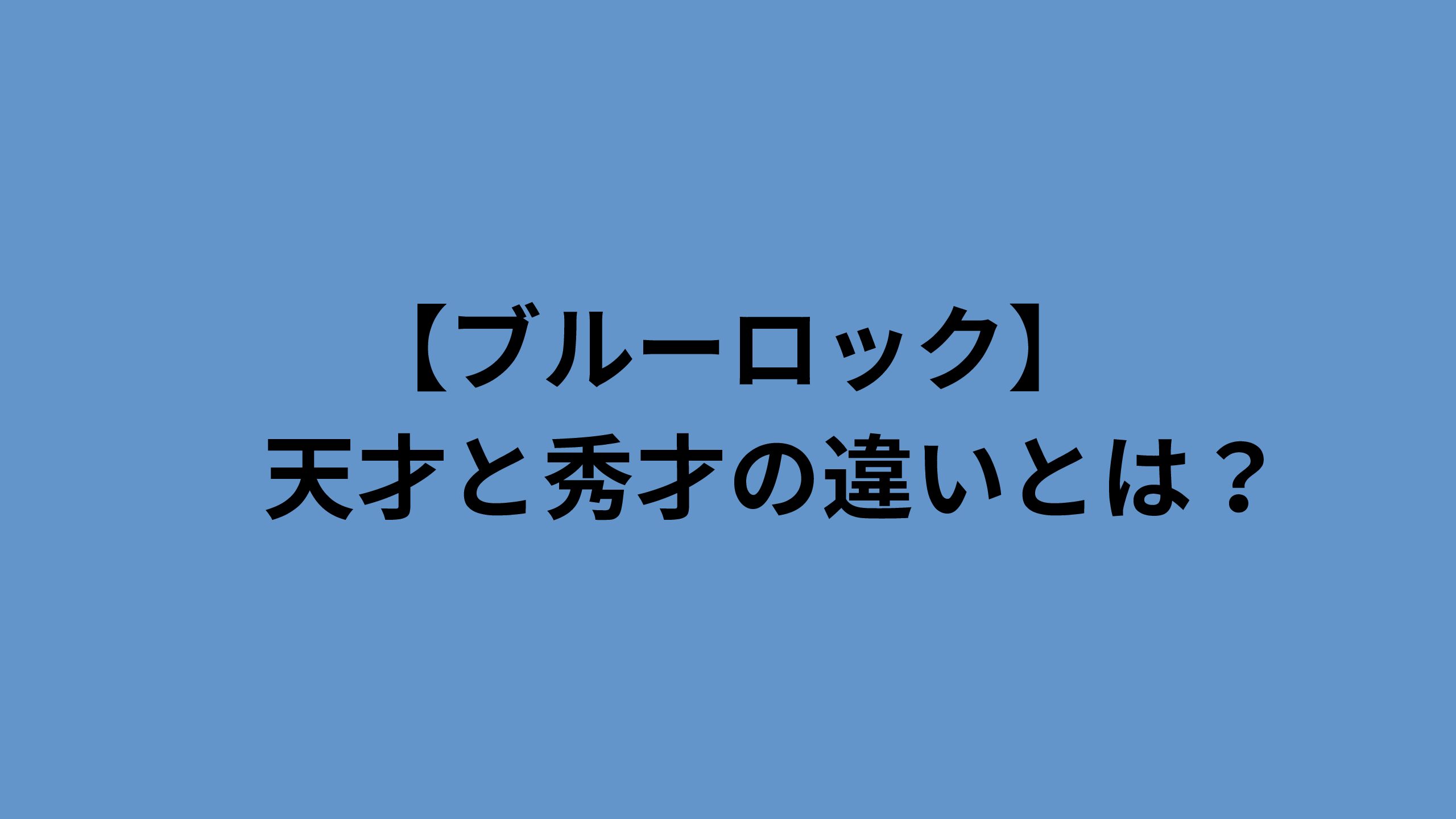
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/442a092b.24afd277.442a092c.ae18db39/?me_id=1229256&item_id=10245795&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmangazenkan%2Fcabinet%2Fsyncip_0062%2Fm1560490043_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)




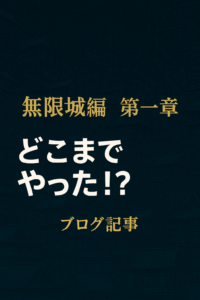
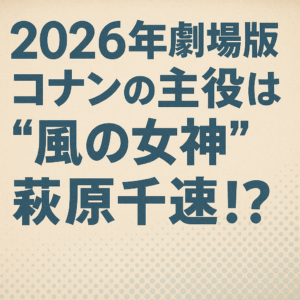
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] あわせて読みたい 天才と秀才の違いとは?【ブルーロック】 本記事にはネタバレが含まれます。 はじめに 『ブルーロック』の281話で新たな哲学、「天才」、「秀才」という概念が […]